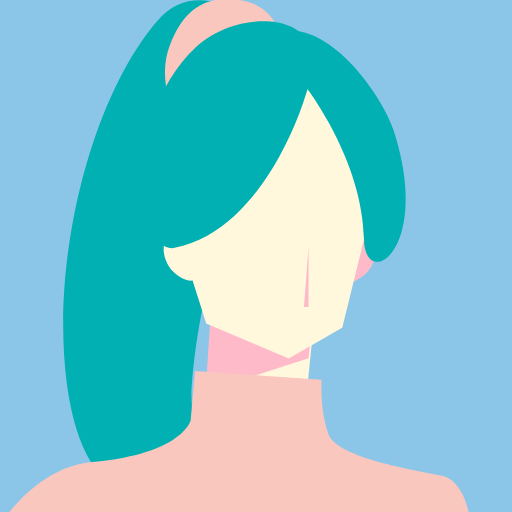もみじ l 妊娠出産メディア編集長 l 切迫早産で3ヶ月自宅安静、3歳児の母 l マタニティケアラー資格取得 l SNSフォロワー1,000人超え
母体からの血液検査のみで胎児の染色体疾患について分かると話題の新型出生前診断(NIPT)。150年以上の歴史を持つ横浜市⽴⼤学附属病院でも検査が可能です。
の新型出生前診断NIPTおすすめクリニック-320x180.png)
横浜市⽴⼤学附属病院ってどんな病院?

150年を超える歴史ある病院
横浜市⽴⼤学附属病院は1871年に現在の病院の前身となる「仮病院」を開設しました。その後改称を繰り返し、現在の横浜市⽴⼤学附属病院と病院名を改めると横浜の医療の中心を担う病院としてその名を馳せています。
各種出生前診断に対応
横浜市⽴⼤学附属病院では以下の出生前診断をはじめとした様々なニーズに対応しています。
- コンバインド検査
- トリプルマーカー検査
- 羊水検査
ひと口に出生前診断といっても、検査対応時期や精度、検査方法などが異なります。どの検査においても妊娠10週以降を申し込み可能としていますので、スケジューリングをしっかり行いましょう。
NIPTにも対応
横浜市⽴⼤学附属病院は2022年7月よりNIPT基幹施設として認定されています。遺伝カウンセリングを行う体制がある、検査前後のフォローができるなど認定を受けるには様々な条件がありますが、横浜市⽴⼤学附属病院はこれらの条件をクリアしていることになります。
検査項目は基本の3項目(21、18、13トリソミー)に限定されるなど制約もありますが、認可施設という安心感を重視する方に選ばれているようです。なお検査にあたってはパートナーの同伴が推奨されています。パートナーはビデオ通話機能での参加も可能ですが、予め予定を合わせることが必要です。
横浜市⽴⼤学附属病院の口コミと評判

横浜市⽴⼤学附属病院の口コミと評判をチェックしてみましょう!
大阪市立総合医療センターの独自口コミ
当サイトが独自に集めた口コミをご紹介します。

NIPT検査を受けた医療施設は?

NIPT検査を受けた決め手やきっかけを教えてください!

NIPT検査を受けてよかったと思う点はありますか?

回答者
夫婦で子育てや価値観について、しっかりと話合うことができたこと。NIPT検査でわかるのは染色体異常の有無だけで、それ以外にも何らかの障害を持って生まれて来る可能性は残り、事前に検査でわかる病気もあればわからないものもあるが、事前にわかることによって、その後の生活・人生設計に関わる知識や心の準備ができるため、出産・子育てに対しての覚悟を決められた気がする。

NIPT検査を悩んでいる方にアドバイスをお願いします!

回答者
NIPT検査で陽性になった場合にどういった選択をする予定なのかは、検査を申し込む前に夫婦でよく話し合っておいたほうがいいと思う。結果云々に関わらず生むつもりであれば、それば子育てのために精神的・環境的事前準備の期間となるし、そうでないのであれば、メンタルケアが必要になることもあるから。NIPT検査は、夫婦間における子育てに関わる覚悟を問われる検査だということを頭に入れておいたほうがいい。
NIPT検査を受けるにあたり、夫婦でしっかりと話し合ったと話されているのが印象的ですね。夫婦での会話はNIPT検査の選択に限らず今後継続的に必要となっていくもの。よりよい生活を送るためにも意識してパートナーとの会話はしていきたいですね。

ここからはネット上での口コミをご紹介します!
横浜市⽴⼤学附属病院の良い口コミ

Googleユーザー
検査で数日間入院しました。先生、看護師さん、看護助手さん、事務の方誠実で親切でした。食事が大変美味しく、びっくりしました。居心地は良かったです。お世話になりまして、有難うございました!
出展:Googleマップ
横浜市⽴⼤学附属病院の悪い口コミ
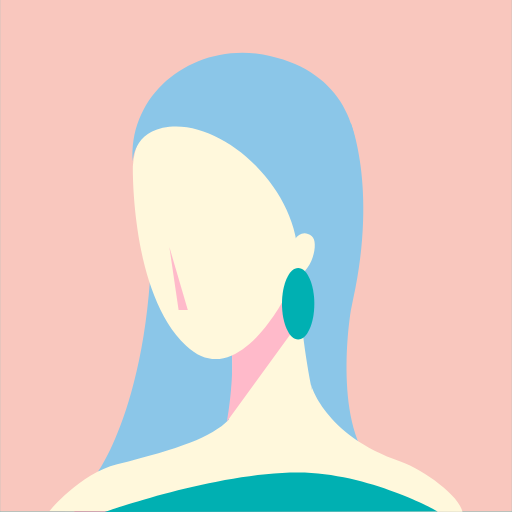
Googleユーザー
紹介状が出て行きましたが、不安で通うのをやめました。 何度違うと言っても、別人のカルテ(パソコン)に記入しているのを見て、怖くなりました。 取り違えられそうで。。
出展:Googleマップ
横浜市⽴⼤学附属病院の費用は?

横浜市⽴⼤学附属病院のNIPTの費用は次のとおりです。
| 検査項目 | 税込金額 |
|---|---|
| 基本検査 (13,18,21トリソミー) | 約12万円 |
遺伝カウンセリング後、検査を受けない場合には遺伝相談料として約1万4千円が必要となります。
横浜市⽴⼤学附属病院の結果はいつ分かる?

結果は検査から約2週間後に外来にて説明がなされるようです。
横浜市⽴⼤学附属病院のアクセス

横浜市⽴⼤学附属病院のアクセスは次のとおりです。
| 住所 | アクセス |
|---|---|
| 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦3丁目9 | 「JR新杉田駅」で下車 → バス |
「京急金沢八景駅」からバスで通院することも可能です。
横浜市⽴⼤学附属病院をおすすめする人

横浜市⽴⼤学附属病院をおすすめする人としない人をチェックしておきましょう!
横浜市⽴⼤学附属病院をおすすめする人
- 神奈川県に在住している方
- 基本検査(21、18、13トリソミー)のみの受検を検討している方
- 他の出生前診断も選択肢として検討したい方
横浜市⽴⼤学附属病院は認可施設となるため、NIPT検査項目は基本項目となる3項目のみです。出生前診断にも各種対応しているため、NIPT意外の検査も視野に入れている方は比較ができおすすめです。
横浜市⽴⼤学附属病院をおすすめしない人
- 体調が安定せず長時間の待ち時間が辛い方
- できるだけ早期にNIPT検査を受けたい方
横浜市⽴⼤学附属病院は大学病院ということもあり、待ち時間が長いという口コミが散見されました。大学美容院は受け入れ人数の多さから待ち時間が長時間化することはある種仕方のないことですが、つわりで体調が安定しない妊婦さんは辛いですよね。
横浜市⽴⼤学附属病院のNIPTについてまとめ
横浜市⽴⼤学附属病院は神奈川県横浜市に150年以上構える歴史ある病院です。これだけ長い期間病院経営が続けてこれたということは地域の方々に受け入れ愛されている証拠ではないでしょうか。
NIPTに関しても認可施設として認定されているため、安心感を重視する方にはおすすめと言えるでしょう。
いかがでしたか?
今回は神奈川県にある横浜市⽴⼤学附属病院についてご紹介しました。検査項目やサポート体制など何を重視したいのかを考え、検討を進めてくださいね。